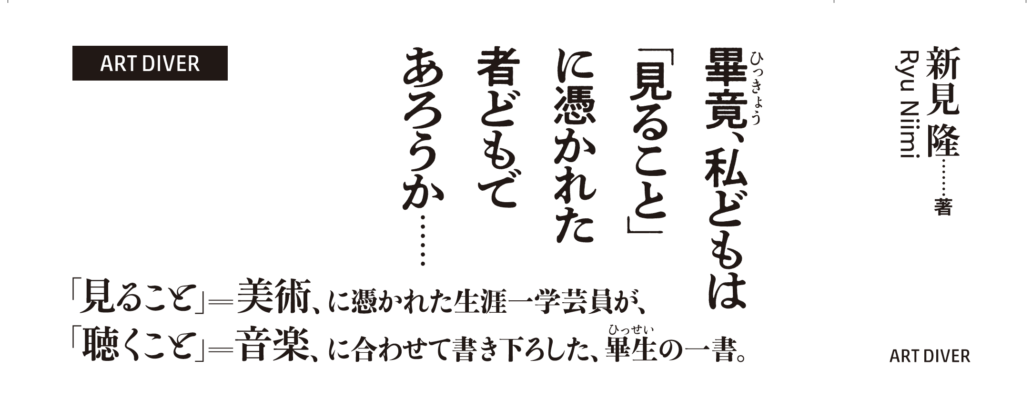編集雑記|新見隆『共感覚への旅 ―モダニズム・同時代論』
いま私たちに必要なのは「作家論」ではないだろうか!?
『共感覚への旅 ―モダニズム・同時代論』という本の企画がスタートしたのが、2022年の8月。それから約1年と8か月の編集・制作期間を経て、ようやくこの4月に完成を迎えます。
総頁392頁の大著です。その内容はというと、モダンアートとコンテンポラリーアートの2章立てで、リヒャルト・ゲルストル、グスタフ・クリムト、オスカー・シュレンマー、ジョルジュ・ルオー、藤田嗣治(レオナール・フジタ)、ジョセフ・アルバース、マーク・ロスコといったモダンアートの巨匠たちにはじまり、同時代(コンテンポラリー)を生きる作家たち―横尾龍彦、西井葉子、椎名絢、関根直子、新見藍、松本陽子、樋口健彦、中村錦平、中村洋子、真島直子、長谷川さち、古石紫織、内田亜里、留守玲、徳丸鏡子、吉雄介、内田あぐり、藤本由紀夫、さかぎしよしおう―の作家論を、もうひとつの軸であり、この書籍のオリジナリティでもある、クラッシック音楽論とともに展開しています。
本書のまえがきにあたる「『表現の影』を求めて―音の香りをきく美術家たち」で、著者は以下のように述べています。
「中世では、音は見るものであり、色も聴くものであって、それは相互に補完するというより、同じ感覚の質を別個の道具で表現し合うもので、つまりは元来は一体のものとして、人間は齟齬を覚えなかったのであろう」(本書、22頁)
「共感覚」と銘打っているのは、この中世における芸術享受のあり方を、モダンアート以降の芸術に見い出す試みです。その鍵となるのが、芸術作品に表れた作家による自然観の表明でした。一般的に、モダンアート以降のアートは反自然的とされ、自然や肉体から切り離すことでアートとして成立しています。しかしそれでもなお、風土や自然、肉体から離れることができなかった表現を、著者は追い求めたのです。
詳細は本書を読んでもらうことにして、ここは編集雑(後)記なので、編集者としての私の所感を少し述べようと思います。
今でこそ、私はアート専門の出版社を運営していますが、美術の世界に足を踏み入れる前は音楽の世界(ソウルとかブルース)にどっぷり浸かっており、「音楽」と「美術」とをつなぐ手だてを長い間探していました。中世に遡らずとも、例えば日本でも数十年前には、音楽や美術、あるいは文学といった多様な芸術が密接に絡みながら、文化をつくりあげていた時代がありました。一方で、現代の芸術表現は縦割り構造となり、互いのジャンルが交わることなくタコツボ化している状況は多くの人が感じているところでしょう。その意味で、本書が提案する「共感覚」は、そんな時代を突破するひとつの切り口になるのではないでしょうか。
私がこの本を出版するに至ったもう一つの重要な動機は、この本が「同時代作家の作家論」であることでした。「批評がない」と言われていたのは遥か前の話で、今はかつてなく批評に溢れる時代であると感じます。そして、その多くは「展覧会評」です。これは批評の舞台の主流がネット媒体であり、展覧会という「イベント」を中心にすることで、少しでも多くの集客を得るといった構造(商売)上の理由があるのでしょう。
展覧会というのは、作家のひとつの世界観の表明ですが、当然それは一側面でしかありません。だからこそ、キャリアを重ねた作家に対しては、制作の遍歴や複数の展覧会をもとに、そこに一貫する表現への批評が必要です。また、ネットメディアの展評は、展覧会ごとに書き手を変える傾向があります。これも読者に目新しさを提供するためのメディア戦略に思えます。しかし、ひとりの批評家が一貫した立場で、長い期間をかけて複数の展覧会や作品の変遷を追うという仕事が重要だと考えています。
この企画が立ち上がった時に、著者から真っ先に言われたのは、「学芸員時代を通して展覧会を企画し、紹介してきた同時代の作家たちについて、しっかりと書き残しておきたい」ということでした。上記の理由から、この言葉に強い共感を覚えたのは言うまでもありません。
そうして出来上がったのがこの書籍ですが、著者は「どこから読んでもらってもいいように書いた」と言います。1節ごとに独立した作家論となっていますので、たしかにどこから読み始めても問題はありませんが、複数の文章を読む中で、筆者のある芸術観が浮かび上がってくることが、さらに重要なポイントです。
いまではオールドスタイルなのかもしれませんが、「批評というのは、立場の表明である」というのが私の考え方です。かつては「論陣を張る」などと言いましたが、論陣を張らず、作家ごと、展覧会ごとに立場をコロコロと変えるような書き手を、はたして批評家と呼べるでしょうか。
今日、しばしば批評自体の意義が問われることがありますが、まずは、各批評家の芸術観の表明がなされることも、そうした議論に必要なピースとなるでしょう。そのためにも多くの作家論が書かれることは、プラスになるのではないか。そうした裏テーマをこの本の出版をとおして、世に問いたいと思っております。
アートダイバー代表 細川英一