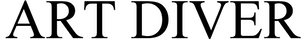メールインタビュー|「シリーズ:美術批評を読む」が目指すものとは? 塚田優、南島興
塚田優(評論家)と南島興(横浜美術館・学芸員)の共同企画となる「シリーズ:美術批評を読む」が、この7月にスタートする。美術批評といえば、「批評の危機」とか「絶滅危惧種」といった言葉で繰り返しその存在の危うさが指摘されてきたが、このシリーズ企画で両者は現状にどういったくさびを打ち込もうとしているのだろうか。塚田と南島にメールインタビューのかたちで、批評を巡る現状認識や企画意図、さらには今後の展開について話を伺った。
― まずはこのレクチャーシリーズが立ち上がるに至った経緯から伺います。聞けば、今年(2024年)の2月に「文化庁アートクリティック事業」(通称)の一環として開催された「レクチャーシリーズ:批評と芸術」(註1)がきっかけとなっているようですね。
塚田 そうですね。あの連続イベントは若手、中堅の美術まわりの書き手がずらりとラインナップされたものだったのですが、ありがたいことに僕も登壇者のひとりとして呼んでもらいました。そのときイベントをオーガナイズされた沢山遼さんが打ち合わせなどでおっしゃっていたのは、書き手同士が互いに顔を合わせたり、発表の機会を設けることの重要性でした。
僕にとって沢山さんは少し上の世代にあたるので、そういう方がああした場を作ってくれた、ということにはすごく考えさせられたんですよね。というのも、沢山さんはどちらかというと、周りを巻き込むというよりかは自分のテキストを書くことに注力してきた人だと思っていたからです。しかしキャリアを重ね、そういった場作りの役割を身近な「先輩」がされていて、自分がそうした振る舞いをするのもありなんじゃないかと思ったのがきっかけです。具体的にどう「文化庁アートクリティック事業」を展開させるかはさておき、連続イベントをなにかの形で継続したいと個人的に考えていたので、打ち上げの席で南島さんに「自分も協力するからなにかやろう!」と半ば勢いまかせに言った記憶があります(笑)。
南島 このレクチャーシリーズは近年稀に見る批評についてのしっかりとした企画でした。じっさい、ぼくはすべての回に参加し、全登壇者の発表を拝聴しましたが、美術メディアやSNSだけでは見えてこない同時代の批評的な焦点、例えば制度批判や様々なインフラストラクチャーに対する批評の必要性などをはっきりと感じることができました。それは同時期に国立西洋美術館「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?」展の公開座談会「現代美術のない美術館で芸術の未来を考える」を拝聴しても感じたもので、なおさらこの時代に共通した課題があると確信できたのはよかったです。ただし今年がはじめてのトライだったこともありレクチャーは20名ほどの会場観覧のみで、その内容は要点をまとめたレポート記事が後日公開されたものの、なかなか企画の内実が見えていないなという印象もありました。なので、それを開いていくという活動がセットであるべきだと思ったので、こんどはオープンかつ、同時代の横に広がる問題意識の共有を含めつつも、歴史の視点、つまり縦軸を意識した批評をめぐる企画ができないかと考えました。塚田さんとともに企画を練り、7月から「美術批評を読む」というレクチャーシリーズを自主企画としてスタートすることにしました。
― 先の「レクチャーシリーズ:批評と芸術」の開催を経て、浮かび上がってきた課題、あるいは批評を巡る現状認識についてもう少し詳しくお話しいただけますか。
塚田 あの企画は良くも悪くも人を集めただけだったので、結果的に対外的な遠心力を持つものにはなりませんでした。もちろん各々がシリアスに思考し、言説を生み出してきた人間が集まりましたから、内容は充実していましたが美術を中心とした視覚文化、および人文系の言説にある程度通じてる必要があったと思います。そこで若い人や、美術のことをもっと知りたいという人でもとっつきやすいようなパッケージを作る必要があると思い、①過去の論者を取り上げる、②登壇者の属性をある程度揃えるという基本コンセプトを「美術批評を読む」では設定することにしたんです。
南島 すでに課題は述べた通りですが、1点付け加えておくと、半ばクローズドでの開催になったのは、主にSNSを舞台として、誰もが予期せぬ炎上や誹謗中傷に巻き込まれかねない現状に対して、まずはそうしたリスクによって自らの主張を抑えてしまうことなく、発表する機会をつくる、という目的があったと聞いていて、それは成功していたと思います。ただ繰り返し言えば、もともと文化庁の事業であることもありますが、アートクリティック事業で得たものは、もっと社会に還元していかなくてはいけないと思います。とっても単純にクローズドのあとはオープンでやる、この往還が必要だということですが、そのなかでぼくはオープンにする役割を感じているので、「美術批評を読む」を企画しました。
ちなみにアートクリティック事業では全レクチャーが終ったあとに以上のような登壇者からの率直な意見を聞く反省会も開かれており、運営面での健全さを感じていることは言い添えておきたいです。
― 今回の「美術批評を読む」ですが、登壇者とレクチャー内容を見ると、「きりとりめでる/多木浩二論、沢山遼/宮川淳論、塚田優/日向あき子論」とあります。1回目となる今回、きりとりめでる(1989-)、沢山遼(1982-)、塚田優(1988-)という1980年代生まれの批評家を選んだ理由を教えてください。また司会をされる南島さんは、この3人の現在の立ち位置をどのように捉えていらっしゃいますか。
南島 本レクチャーシリーズの登壇者は塚田さんと検討してお声がけしています。初回の登壇者はあらかじめ年代で区切ったわけではありませんが、たまたま80年代生まれの3名になりました。とはいえ、中堅かそれより下の若い世代の批評の担い手が登場しているにもかかわらず、それぞれの問題意識や立ち位置が見えないために、美術批評という営為全体が漠然としたものに捉えられている現状へのアクションという意識はありました。その点は、アートクリティック事業と共通するものです。
では、なぜ80年代以降の世代の活動が見えづらいかと言えば、SNSの前面化と批評と呼ばれる活動の多様化があると思っています。批評とは現象的に捉えれば、何かと何かの間に発生するものだと言えます。作品と作品、展覧会と展覧会、研究と研究などの間に生まれ、また批評によって、あるふたつの表現を繋げる間の空間が作り出されるわけです。しかし、いまはあらゆる情報がダイレクトに交換、売買することができて、そしてそうした直接性がよいと信じられている時代です。すると必然的に中間項においてある解釈を生み出し、ときに不透明な価値判断の温床にもなる批評は不要になります。またそれまで批評家と呼ばれていたはずのひとたちがもはや「批評家」とは名乗らず、しかし批評的な意志を持って活動している。その最たる例がキュレーターだと思います。いまの情報環境に適応するのであればふつうは批評家ではなく、キュレーターになって批評的な展覧会を企画するはずです。批評において直接性を担うとは、そのような選択をすることだとも思います。逆にいえば今日、批評家であると名乗るひとびとは漏れなく不自然な選択をしています、とまで言うと反論があるでしょうが、それぐらい批評家という存在は奇妙なものだということです。
前置きが長くなりましたが、きりとりめでるさん、沢山遼さん、そして共同主催者の塚田優さんのお三方についてですね。まず、きりとりめでるさんは批評の仕事に限定すれば、現場批評の担い手と言っていいと思います。また美術批評誌『パンのパン』を刊行し、批評の場所をみずから立ち上げている点で、美術批評の領分をしっかりと確保しようとする姿勢も印象的です。沢山さんは戦後の美術批評史、また批評理論にきわめて自覚的な批評家だと思います。『絵画の力学』ではフォーマリズムを理論的な起点にしながら、それ自体を拡張するスタイルが貫かれていました。塚田さんはデビュー論文である「キャラクターを、見ている」ではキャラクター表現の臨界、近年は「アート」とイラストレーションやデザイン史との境界をひもとく研究をされていて、ある表現やジャンル同士の隙間に批評を見出すと同時に、美術批評の俎上に上りづらいイラストレーションやデザインの歴史について平易に語る研究者でもあると思います。
塚田 イベントのタイトルがタイトルなので、1回目は直球で、ストレートをずばっと投げ込みたかったというところはあります。とはいえすでにある程度の回顧がなされている御三家(註2)ではなく、その周辺に肉付けするようなイメージを個人的には持っていました。そうなったときに思い浮かんだのがこのメンバーだったという感じです。
同じ書き手として沢山さんの文章は構造の提示に長けていると思っているので、文体含め独特のフォルムを持つ宮川淳を論じてくれるのは非常に楽しみです。きりとりさんの仕事からは、文化の布置がどのように作品や展覧会に凝集しているかを見出す眼力にいつも感嘆させられていますが、そのような視点を彼女が持てるのも、写真という美術の周縁ジャンルに深い造詣を持っているからです。そんなきりとりさんが知の巨人、多木浩二をどう論じるのかに注目です。僕は日向あき子について、メディア論やジェンダー、イラストレーションといったキーワードをもとに考察する予定です。
― イベントでは3時間の開催時間が予定されていますが、どのようなタイムスケジュールとなるのでしょうか。
南島 はじめに3名に30分ずつそれぞれひとりの批評家についてレクチャーをしていただきます。その後、休憩を挟み、90分ほど全体討議というスケジュールになります。前半と後半で適宜、質疑応答を設ける予定です。
塚田 討議の時間も設けてるので、補足などもしつつもイベントならではの化学反応が起こることを期待しています。南島さんのXの投稿を見ると彼なりのテーマ性を持ってのぞんでくれそうなので、司会っぷりにも期待してください(笑)。それと会場からも活発な応答があるといいなと思っています。
― 今回の企画のポイントとして、過去に活躍した批評家と現役の批評家とを結ぶリンクを可視化することに重きが置かれていますが、そのことで現在の批評シーンにどのような効果や展開を狙っていますか。
塚田 イベントでは現役のプレイヤーが、過去の論者を語るという分かりやすい構図が生まれます。これは実のところ、理論を人称的な関係性に矮小化する暴力も孕んでいます。しかしそういうふうに半ば無理やり提示することによって、聞いてる側に見出せることがあるんじゃないかなと。そういった人への興味から始めてもらって、理論的な理解は事後的に追いついてもらえば良い。初学者にとってみたら美術批評とひとくちにいっても色々ありすぎて、誰のなにを読めばいいかわからない。とにかく現代は情報が多すぎるんです。それによって、何が何と繋がってるかが分からなくなっている。だからどんな効果を狙っているかといえば、見てくれた人に批評という宇宙にダイブするきっかけを与えられたらと思っています。
南島 ぼく自身も恥ずかしながら、塚田さんが取り上げるまで日向あき子の著作は読んだことがありませんでした。いま急いで、デビュー作の『ニュー・エロティシズム宣言』や『ウィルスと他者の世紀』などを取り寄せて読んでいます。日向はフェミニズム批評とも並走していた論者であり、そこにポストモダン思想における電子メディア論が合流している。例えば、いまちょうど読んでいる『ウィルスと他者の世紀』ではダナ・ハラウェイ『サイボーグ・フェミニズム』に共感しつつ、ハラウェイの「センス」は日向がデビュー作『ニュー・エロティシズム宣言』以来論じてきた情報時代ではなく、機械時代のものではないかと疑問を呈しているところなんかは興味深いです。実際にはサイボーグ・フェミニズムには様々な学問的な広がりがあるので、これは自論の位置をクリアにするための一種の戦略的な言説にも思えますが、しかしそこまでして、日向が20世紀末に希望を見出した情報社会とはなんだったのでしょう。今日の情報社会はマルクーゼやマクルーハンらの思想的背景のもと、日向が夢見た新しいエロティシズムを生み出しうる環境とはまた異なった姿をしているはずです。そんなことも含めて、当日は議論できればと思っています。
― イベントサイトには、2か月に1回の開催と書かれていますが、今後も、「現役の批評家が、過去の国内批評を論じる」といった対応関係でのレクチャーが続いていく予定ですか。
南島 第2回は3名の作家をお呼びして、美術批評家について論じていただく予定です。それ以降はテーマを検討中ですが、現代哲学や建築、ポピュラー音楽の批評家や研究者をお呼びすることも考えています。様々な視点から、美術批評の枠をこえた批評のネットワークが編成できるラインナップになればと思っています。
塚田 次回以降もいろんな人を呼びたいし、ある程度柔軟に、美術に関するテキストを少しでも書いてる人なら取り上げても大丈夫ぐらいの幅は持たせるつもりです。それに番外編的な回もあってもいいかもしれません。南島さんと話していると、アイデアは無限に出てきます(笑)。ひとりでも多くの人に参加してもらって、登壇者・聴講者みんなでこのシリーズを育てていければと思っています。
(2024年7月収録)
註1
「レクチャーシリーズ:批評と芸術」(2024年2月3日、10日、17日開催)
http://ycassociates.co.jp/critics/2024/01/10/1903
3回のレクチャーの登壇者は以下。
第1回「変異する文化史」 2024年2月3日(土)レクチャラー|きりとりめでる、gnck、仲山ひふみ
第2回「行為と行為者」2024年2月10日(土)レクチャラー|大岩雄典、関貴尚、高橋沙也葉
第3回「表象の肌理」2024年2月17日(土)レクチャラー|高嶋慈、塚田優、南島興、村上由鶴
註2
美術批評の御三家とは、針生一郎(1925-2010)、東野芳明(1930-2005)、中原佑介(1931-2011)のこと。
【イベント概要】
シリーズ:美術批評を読む 第1回「批評家が批評を読む」
日時:2024年7月28日(日)12時30分~15時30分
会場:ネイキッドロフトヨコハマ ※配信あり(ツイキャス/2週間のアーカイブ)
住所:神奈川県横浜市西区南幸2-1-22 相鉄ムービル3階
料金:会場 1,500円(当日2,000円)※飲食代別、1オーダー制
配信 1,000円
https://www.loft-prj.co.jp/schedule/naked/285510
登壇者プロフィール
きりとりめでる
1989年⽣まれ。デジタル写真論の視点を中心に研究、企画、執筆を⾏なっている。著書に『インスタグラムと現代視覚⽂化論』(共編著、BNN新社、2018)がある。2022年に「T3 Photo Festival Tokyo2022」のゲストキュレーター、『写真批評』(東京綜合写真専門学校出版局、2023)の編集委員を務めた。2024年には『パンのパン4(下)』を発行予定。ウェブマガジン「artscape」の月評を担当。AICA会員。 @kiritorimederu (X/旧Twitter)|@kiritorimederu(Instagram)
沢山遼
美術批評家。1982年岡山県生まれ。武蔵野美術大学大学院造形研究科修士課程修了。2009年「レイバー・ワーク―カール・アンドレにおける制作の概念」で美術出版社主催「第14回芸術評論募集」第一席。単著に『絵画の力学』(書肆侃侃房、2020)、主な共著に『絵画との契約 山田正亮再考』(松浦寿夫ほか、水声社、2016)『現代アート10講』(田中正之編、武蔵野美術大学出版局、2017)などがある。Yumiko Chiba Associatesが主宰する批評集『クリティカル・アーカイブ』のシリーズの監修も行う。令和2年度文化庁「新進芸術家海外研修制度」研修員としてニューヨークに滞在。
塚田優
評論家。1988年生まれ。主な共著に『グラフィックデザイン・ブックガイド』(グラフィック社、2022)、最近の論文に「1980年代におけるイラストレーターの社会的立ち位置とイラストレーション言説をめぐる研究」(『DNP文化振興財団学術研究助成紀要』第5号)がある。 ytsukada.themedia.jp|@yasashiiseikatu (X/旧Twitter)
南島興
横浜美術館学芸員。1994年生まれ。東京藝術大学大学院美術研究科修士課程修了(西洋美術史)。全国の常設展をレビューするプロジェクト「これぽーと」運営。時評番組「みなみしまの芸術時評」主宰。旅行誌を擬態する批評誌『LOCUST』編集部。『坂口恭平の心学校』(晶文社、2023)刊行。