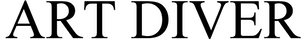著者インタビュー|小森真樹「史実と展覧会の『再演』の先に目指すものとは?」
第2次世界大戦直後の1946年、GHQによって開催され、占領軍関係者のみが入場を許された「日本の戦争美術」展。美術館を会場にしたこの展覧会には、戦時中に日本の画家によって描かれた「戦争画」が所狭しと敷き詰められ、これらの絵画が保存すべき「芸術」なのか廃棄すべき「プロパガンダ」なのかが検収されたという。映像作家の藤井光は、この「日本の戦争美術」展の史実を入念にリサーチし作品化。1946年の「日本の戦争美術」展を会場に再現した絵画展に、歴史史料からシナリオを起こした対話劇型の映像インスタレーションを加え、2022年に東京都現代美術館で〈日本の戦争美術〉展として発表した。さらにコロナ禍の影響が残る2023年には、ウェブ上のバーチャル展覧会として同展を開催している。
この2つの展覧会をふまえ、2024年3月に武蔵大学で平日5日間限定で開催されたのが、本書の元となった「美大じゃない大学で美術展をつくる|vol.1 藤井光〈日本の戦争美術1946〉展を再演する」である。ここでは、同展の企画者であり、本書の編著者である小森真樹にインタビューをおこない、小森の研究分野やこれまでの活動を伺うと共に、〈日本の戦争美術1946〉を作家でない立場から再演した経緯や意義を尋ねた。
テキスト:相嵜颯、細川英一(ART DIVER)
ー 小森さんの専門である「ミュージアム研究」とはどのような学問なのでしょうか?
ミュージアム研究という言葉はなかなか聞きなれないかもしれませんが、例えば「博物館や美術館が物をどのように定義してきたのか」といった点に着目して、ミュージアムという制度や展示行為について文化的・社会的な問題として探究する学問分野を指します。比較的新しい分野で、運営制度に関する実学的な性格が強い「博物館学」と区別して呼ばれることもあります。
例えば、私が博士論文で取り組んだムター博物館は、およそ150年前に設立された全米初の医学博物館です。そこにはさまざまな症例の人体がコレクションされています。元々は多くの症例を集めて治療法を研究するための専門機関でしたが、治療法の確立とともに研究機能がなくなり、しだいにコレクションのみが残る状況となりました。しかし、収集された人体は簡単に捨てることはできません。日本語でも「遺棄」と特殊な用語が当てられるように、人体の扱いとは一種のタブーを含む特殊な行為です。そのとき、コレクションの意義を時代にあわせて更新する必要性が生じました。その結果、1990年代には人体をモチーフしたオリジナルグッズが販売されるようになりました。これは、博物館の位置するフィラデルフィア地域の観光化事業の一環として推進されたものでもあります。その人体グッズには、例えば、結合双生児、俗に「シャム双生児」と呼ばれる二つの頭部を持って生まれた患者の症例をモチーフにしたクッキー型があります。これはミュージアムグッズとして最も人気を博しましたが、同時に「障害者」の人体を商品化したとして倫理的な批判も起こりました。研究のために集められた人体が、ミュージアムの「経済資本のリソース」として扱われ始めたわけです。
以降、ムター博物館では「人体をいかにミュージアムで扱うのか」といった議論が、時代的な感覚や、関係する人びとの意向を含めたかたちで盛んに繰り広げられています。つまり、コレクションに関する議論の変遷を追うことで、時代ごとの倫理的な価値観が見えてくるのです。これは一例ですが、ミュージアム研究では、展示品のみならずミュージアムの制度的な議論に注目することで、社会全体の価値観を考察することに主眼を起きます。
ー 博物館を通して社会の倫理について考えることが小森さんが重視されるミュージアム研究とのことですが、小森さんがミュージアム研究を専門とするに至った動機について教えてください。
ミュージアムには優れた学術的知識を社会へと「開く」特性があります。知らない地域のミュージアムに行くと、その土地の歴史や政治に関する高度な知識をゼロから学ぶことができます。多くの人と同様、私にとってもミュージアムは専門的な知見を効率的に学ぶことができるお気に入りのツールです。
その一方で、ミュージアムを研究対象としてみたとき、その「開かれる」という側面を批判的にも捉えてみたいと考えています。ミュージアムは学問を市民に公開するという近代以降の民主化や共和制と深く結びついており、ポジティブな面が強調される傾向がありますが、はたしてミュージアムにおける「開かれる」性質は社会の民主化にとって良いばかりなのか、もしかしたら阻害する側面があるのではないか。こうした批判的な視点にあえて立つことが私のミュージアム研究の基本にあり、その上で「いかにミュージアムで民主的な社会を築けるのか」という問いを考えることが、私がミュージアム研究をする動機になっています。
ー 小森さんはミュージアム研究のみならず、同時代の政治・社会の批評にも注力されていますね。
私の活動は大きく分けて、研究、批評、企画の3つで構成されています。アカデミックな研究は立証や正確さや専門性が求められますから、どうしても関わる範囲が狭くなってしまいます。そこで、いわゆる学問的な方法とは異なるやり方でクリエイティヴィティを発揮するために、批評をしたり、さまざまな企画に関わっています。
批評に関しては最近、『楽しい政治 「つくられた歴史」と「つくる現場」から知る』(講談社、2024年)という書籍を刊行しました。ポピュラーカルチャーにどのような政治的機能があるのかについて興味があり、この本ではあえて大衆文化が担う政治性のポジティブな部分を強調して書いています。アメリカの地域研究を始めて気がついたのですが、アメリカでは人権問題やジェンダー的な摩擦など価値観の対立する問題について文化――とくに大衆文化のなかで改善していくという動きがかなり多く見られます。ドラマや映画の中には、言葉で解説をしたりするような説明的なものではなく、人種や性の差別などといった社会問題やその背景にある歴史について静かに、だが雄弁に語るシーンが数多くあるのです。こうした作品に潜在した政治性を「見える化」することが、批評の大切な役割のひとつだと考えています。もちろん優れた営みはあるものの、社会全体では日本はまだ「見える化」が少ない。それは、作品や制度の中に埋没した政治性を読み解くための「文法」が、日本にはまだ浸透していないということでもあります。アメリカの事例を日本語で紹介することによって、こうした「見える化」の過程が日本の様々な領域で起これば良いと願い、この本を出版しました。
ー 「企画」の活動ではどのようなことを目指されているのでしょうか?
アートプロジェクトやワークショップの企画、ウェブマガジンの編集、今回であれば展覧会の企画をするといったように、ひとつのメディアにとらわれずに、素人的な感覚でアイデアを具現化することを大事にしています。
例えば、今回書籍デザインを担当してくれた三宅航太郎さんとは、一緒に岡山県の空き物件を借りて「かじこ」(2010年7月-10月)というオルタナティブスペースをつくったことがあります。このプロジェクトは、アーティストが滞在して制作できる「アーティスト・イン・レジデンス」であり、来館者が低いハードルでトークイベントなどを企画できる環境や制度を整えた「イベントスペース」であり、周辺地域の人たちにとっては「公民館」として使える「開かれた」多機能スペースを目指しました。「かじこ」に参加してくれたアーティストの西野正将さんとは、今度「美大じゃない大学で展示を作る」展の第3弾として2025年の8月に展覧会を行います(「SOS 応答と対話で『何か』を探す」展。西野正将・ふくだぺろを参加作家に、2025年8月30日・31日表象文化論学会大会企画として武蔵大学にて開催)。
それから今回の書籍の起点ともなった企画として、触れなくてはいけないのが、一橋大学の歴史学者牧田義也さんが主体となった「Project Intersection」(2018年)というツアーパフォーマンス+ワークショップです。藤井光さんと私の最初のコラボレーションの機会となり、私は牧田さんとともにモデレーターとなり、藤井さんはパネリストとして参加しました。クリエイティブセンター大阪を会場に開催されたのですが、ここは元々名村造船所跡地という場所で、朝鮮半島等、さまざまな地域の出身者が、「徴用工」として強制労働させられていたという歴史が忘れられつつあった土地でもありました。藤井さんにはガイド役をお願いし、土地が持つ記憶を想起するといったワークショップを実施していただきました。
ー そういった企画の積み重なりのなかで本書籍の出発点になった藤井光さんの作品〈日本の戦争美術1946〉(2022年)をご覧になるわけですね。
そうです。この頃は「ミュージアム研究」をある程度続けてきた時期でもあり、展覧会を「する側」の構造から作品を分析するという独自のフレームを得られた頃でもありました。藤井さんの作品はそれまでも継続的に観てきたのですが、東京都現代美術館で展示された〈日本の戦争美術1946〉に関してはミュージアム研究の立場からみて極めて面白いと感じました。この展覧会や作品の意義については、本に収録した「『パブリック』ミュージアムから歴史を裏返す」に詳しく書きましたのでここでは触れませんが、初めて鑑賞したときには、まさか自分がこの作品を元に展覧会を企画するとは思ってもいませんでした(笑)。
美術館での展示の翌2023年に、藤井さんは「日本の戦争美術1946展 Cloud Exhibition」として、同展をオンラインに展開し、美術館で展示した作品群を小品につくりかえ、販売をおこないました。私はそこで「戦争画」のリーダー的存在だった藤田嗣治の作品をモチーフにした小作品を購入したんです。藤田は日本からフランスに渡って自らのアイデンティティを変えていくわけですが、そうした「移民史」や「トランスナショナル」の視座はアメリカの地域研究に触れてきた私にとっては馴染みがあり重要なものだと自然と感じていました。国家間でアイデンティティが裂かれた藤田の人生に対して関心があったというのも、153点もあった作品のなかでもこれを購入に至った理由のひとつです。
そもそも美術館で展示した〈日本の戦争美術1946〉それ自体が、1946年に実際にあった「日本の戦争美術」という展覧会の「再演」であったわけですが、このときはさらにその「再演」をネット上で展開しているわけです。しかも作品が購入可能となっていて、私たちは藤井さんが再演をおこなっている「歴史」に参加する機会を得ることができた。そのあり方に感銘を受けて作品を買ったわけですが、そのことを詳しく論じたのが、「美術品をポチって戦争の記憶に参加する」という本書所収の論考です。
ー 〈日本の戦争美術1946〉を購入することで歴史に「参加」した小森さんが、そこからさらに一歩踏み込んで、「作者ではない」立場から展覧会を企画し、歴史の「再演」をしようとされたのはなぜでしょうか。
もともと、多くの制約がある総合大学の中で展覧会を企画すること自体に以前から興味がありました。コロナ禍の状況下では学生と一緒にオンライン展覧会を企画したこともありましたが、いざ実際の空間で展示することに対しては、展示としての質の担保などの面から踏み切れずにいました。
そんななか藤井さんの〈日本の戦争美術1946〉の作品を購入したのですが、そこには思いがけず、映像作品の上映権がついていたんですね。本にも収録したシンポジウム内で藤井さんは、上映権をつけたことに対して、「誰でも気楽に自宅に展示していただきたい」「絵画だったら家で観たりしますが、インスタレーション作品だとなかなか難しい。この点をもう少し開いて、誰でも展示できる、作品の民主化を考えたからだ」と語っています。実際には藤井さんは小規模な上映会などを想定していたらしいのですが、そこを私が展覧会にまで規模を大きくしてしまいました(笑)。ただ、実際やってみるとめちゃくちゃ大変で……。規模もこんなに大きなものになることは自分でも最初は想定していませんでしたし、探り探りの状況でだんだんと大きくなってしまった感じです。目の前にある条件によって思考が決まっていく、文化人類学でいう「ブリコラージュ」的なキュレーションだったと思います。私にとっては多くの制約を工夫して潜り抜ける展覧会制作に興味があったのだと振り返っています。
この傾向は、展覧会に合わせて開催したシンポジウムにも当てはまります。ちょうど展覧会開催の年に退官される香川檀先生は以前、藤井さんと《核と物》(2017年)という作品でコラボレーションしており、かつ退官記念のイベントをされる時期だったので、せっかくだったらシンポジウムとして対談していただきたいと考えました。それに合わせて展示の内容を少し変えるなど、かなり偶発的な出来事を受け入れながら展覧会をブリコラージュしていきました。
ー 今回の本の中では「シンポジウム」の章にも大きなページを割いているのが特徴ですね。
展覧会のコンセプトを練り上げていくなかで、この企画は記録集をつくることは必須だと考えはじめていて、そこで鍵になるのがアーティスト本人の言葉でした。藤井さんは、常に彼の言葉が作品そのもののような語り方をしますし、その言葉は多くの人にパワフルに響くものです。ですから、彼の言葉そのものを本に掲載することが重要でした。
そして藤井光というアーティストは、メインストリームの歴史とは異なる歴史を開いていくなかで、それを他人がどう引き受けて再度語っていくのかということについて考え続けてきました。この「他者に歴史を開く」というテーマそのものが今回制作した記録集のテーマとも重なっていて、それには学術的な論文よりも座談によって本人の言葉として発信されるほうが適していると考えたのです。
収録したシンポジウムは2本。先に述べた香川檀先生と藤井光さんとの対談に加え、藤井作品を熟知され、以前の対談でも藤井さんの思考や作品の意義を優れた視点から引き出していた星野太さんをお招きしました。2本とも、その場限りのトーク「ショー」といった趣きではなく、未来につながる論点がいくつもその場で生まれる素晴らしいシンポジウムが収録できたと思います。
ー 最後に、この本をどういう人に読んでもらいたいですか。
これまで藤井光の作品を追いかけてきたアートファンはもちろんですが、藤井光や〈日本の戦争美術1946〉という作品についてまったく知らなかった人にも読んでもらいたいですね。もともと1946年に開かれたオリジナルの〈日本の戦争美術〉展は、GHQによって開催され、占領軍関係者のみが入場を許された展覧会でした。この隠された史実を扱った藤井光の〈日本の戦争美術1946〉は、繰り返し再演されることで、その史実が開かれ、民主化していく構造にあります。
この本自体が、〈日本の戦争美術1946〉のひとつの「再演」ですが、より多くの時空間にこの本が「開かれる」ことによって、また新たな「再演」が起きてほしい。展覧会は平日5日間というエフェメラル(儚い)なものでしたが、〈日本の戦争美術〉を歴史に残すためには、ISBNコードをつけ、本屋や図書館に広く行きわたることが私にとって重要だったのです。現在研究員をやっているテンプル大学など海外のいくつかの図書館にも所収してもらいましたが、日英バイリンガルにすることでコンテクストを複数化したり、単行本の形式をとり、また比較的購入しやすい価格帯に抑えることで多くの人に読んでもらえる仕様にしたことで、この本を読む人が増えて、どこかで思いもかけない「再演」が起こることを願っています。
(2025年3月1日、オンラインにて収録)
小森真樹(こもり・まさき)
1982年岡山生まれ。武蔵大学人文学部教授、立教大学アメリカ研究所所員、ウェルカムコレクション(ロンドン)及びテンプル大学歴史学部(フィラデルフィア)客員研究員。アメリカ文化研究およびミュージアム研究。特に博物館や美術館における歴史の再構築や展示の政治性に関心をもっている。キュレーション、雑誌編集、批評にも携わる。主著に、『楽しい政治 「つくられた歴史」と「つくる現場」から現代を知る』(講談社、2024年)、「ミュージアムで『キャンセルカルチャー』は起こったのか?」(『人文学会雑誌』武蔵大学人文学部、2024)、「共時間とコモンズ」(『広告』博報堂、2023)、「美術館の近代を〈遊び〉で逆なでする」(『あいちトリエンナーレ 2019 ラーニング記録集』)など。。企画に、古民家を活用したゲストハウス型プロジェクト『かじこ|旅する場所の108日の記録』(三宅航太郎、蛇谷りえと共著、2010)、『美大じゃない大学で美術展をつくる|vol.1 藤井光〈日本の戦争美術 1946〉展を再演する』(ART DIVER、2025年)、ウェブマガジン〈-oid〉(2022-)など。