「表現の影」を求めて―音の香りをきく美術家たち
序章:「自然観としての共感覚」
序にかえて―失われた「五感」への旅、あるいはクリュニー修道院のボードレール
1章:「故郷喪失の旅、モダン編」─美術と音楽の同時代性
01 光の奇蹟―田中希代子のサン=サーンス、あるいは岡崎京子の孤独
02 宇宙の咆哮に向かって―私における、アントン・ブルックナー
03 理性でも、情念でもないもの―凡庸な革命家シェーンベルクと、彼の妻を寝取った天才ゲルストルの場合
04 「変容」と「窓の絵」―そこに世界のディテールはあったか、リヒャルト・シュトラウス先生よとオスカー教授宣う
05 狂気の中の慰藉―ヴィヴァルディ、そしてピラネージ
06 世の果てにあるエロス―ルオーとメシアンの場合
07黄金のシューベルト、あるいは宇宙への階梯―田部京子に。
08 神秘主義は正方形がお好き―アルバースとスクリャービンの場合
09 白旗でない、白い世界への退却―プロコフィエフから、マレーヴィッチの至高主義(シュプレマティズム)をみると
10 火の叫びのロスコ―それをしも、唯一無二の女神ブリュンヒルデに捧げるか
2章:「共感覚への旅」─同時代作家論
01 天の龍、天の舞踊―横尾龍彦の霊画、あるいはドイツ表現主義の彼方
02 世紀末の女神ペヤチェヴィッチ―西井葉子の黒いロマンティシズムに
03 ラヴェルに誘われ、夜の海へ―椎名絢の球体絵
04 愛の抽象性について―関根直子の鉛筆画、あるいは「トリスタンとイゾルデ」
05 愛の自己許容を超えられるか?、新たなる表現主義―新見藍の陶彫が、エゴン・シーレに出会う時
06 「宇宙エーテル体」―松本陽子の黙示録的空間
07 天から降るものの表情について―樋口健彦の彫刻に
08 多面性としてのショスタコーヴィッチ―中村錦平・中村洋子夫妻に
09 楽園への逃走―真島直子の仕事
10 沈黙の絵画、あるいは目の舞踊の石―関根直子と「トゥーランガリラ」、長谷川さちとヴェーベルンの香り
11 覚醒、または肉体の放棄―古石紫織のドビュッシー青、そして「左手」
12 風景の故郷喪失(ディアスポラ)―内田亜里、あるいは写真の始原への問い
13 小動物になった惑星―留守玲とバルトーク
14 卵形の供物―徳丸鏡子を、ストラヴィンスキーからみると
15 哲学するトタン―吉雄介のバッハ風彫刻
16 自然の怒りについて―内田あぐり、あるいはベルクの表現主義
17 デュシャンの星のもとに―音の作家、藤本由紀夫
18 Yell ―さかぎしよしおう、あるいは、いきものがかり
現代作家略歴
これが最後なのか? いやなーに、まだただの始まりなんだろうサ。
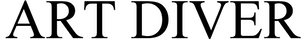
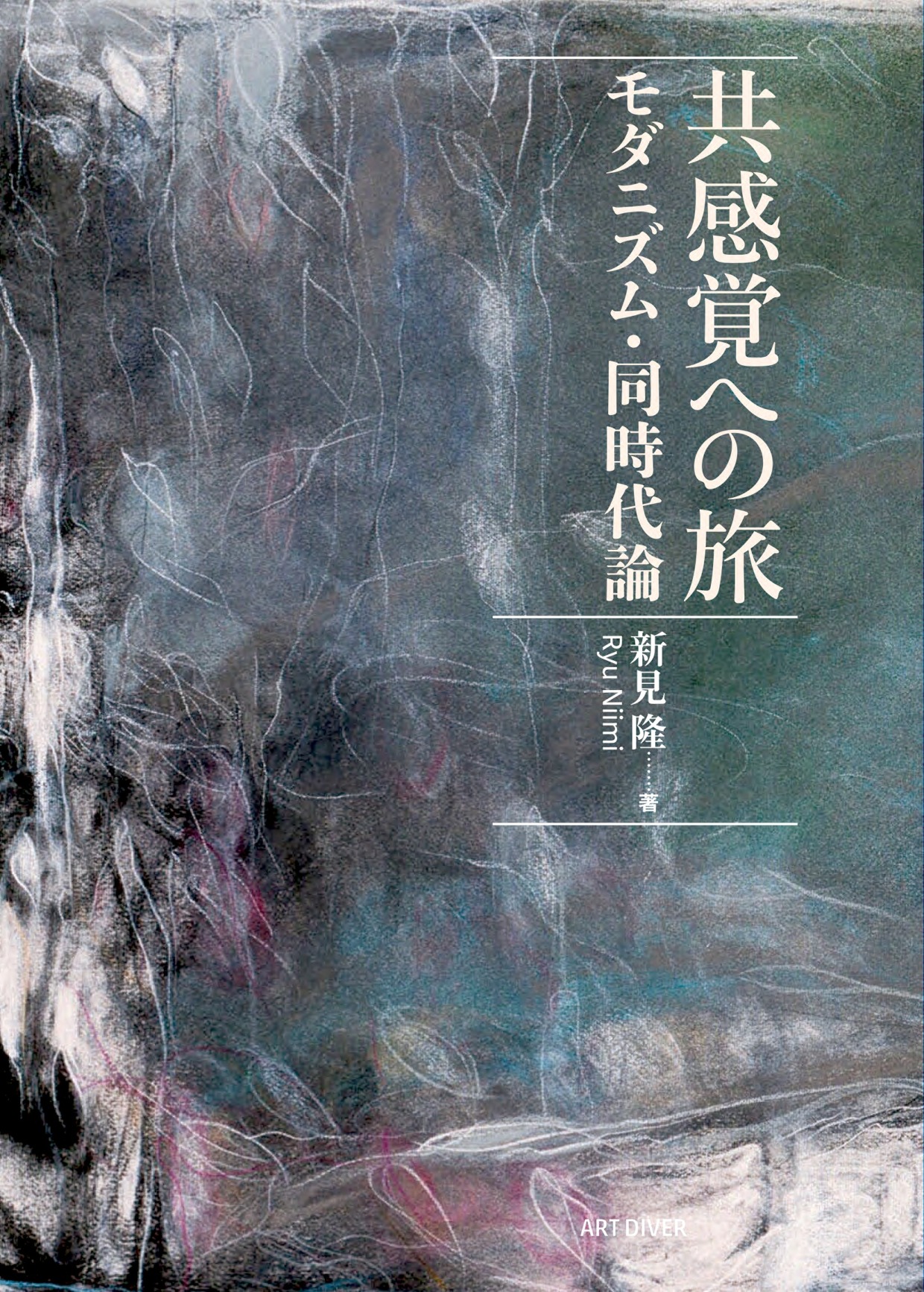
美術勉強中 (承認)
豊かな知識と自由な思考で音楽、美術、文学などを横断的に結びつける、大変おもしろい内容でした。
難しく感じるところもあった分「もう一度読んで理解を深めたい」と思ってしまう本です。
最後、芸術の持つ力について言及されているところで胸が震えました。
これっと
造本、テキストともに格調高く美しい本です。
でも、文章はわかりやすく、むずかしくはありません。
筆者が芸術を信じるその姿勢、選ばれた作家たちがなにをもって選ばれているのかといった審美眼がこの本を貫いています。
ひとりの学芸員の生き様とでもいえる渾身の一冊ではないでしょうか。
この本をテキストに、ここに選ばれた作家たちの作品を見たくなりました。