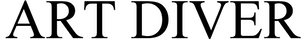著者インタビュー|琴 仙姫(クム ソニ)「なぜ『朝露』プロジェクトは始まったのか?」
社会的な主題を扱うソーシャリー・エンゲイジド・アート(SEA)が隆盛となって久しいが、琴仙姫の「朝露」プロジェクトは数多あるSEAのなかでも、極めてオリジナルな輝きを放っている。自身のルーツから出発しながら、東アジアの歴史問題にアートの手法で向き合い、普遍的な美を引き寄せることに成功している。ここでは本プロジェクトを書籍化した琴仙姫『朝露 ―日本に住む脱北した元「帰国者」と アーティストとの共同プロジェクト』の刊行を記念し、著者インタビューをおこなった。
テキスト:細川英一(ART DIVER)
― 本の副題にもあるように、このプロジェクトでは「元『帰国者』」という方の存在がとても重要となっています。私たちには聞き慣れない言葉ですが、「元『帰国者』」とはどういった方々なのでしょうか。
琴 前提としてお話しすべきものに、1950年代末から1980年代前半にかけておこなわれた「在日コリアンの帰国事業」があります。本の中で山本浩貴さんが詳しく書かれていますので、ここでは簡単に触れるだけにしますが、主に朝日政府と赤十字の主導のもとにおこなわれたこの事業では、実施された25年余りで総計9万人を超える在日コリアンとその家族たちが北朝鮮に渡ったとされています。このとき北朝鮮に移民した方のことを、北朝鮮では「帰国者」と呼びました。「帰国者」はロシアの船で北朝鮮へと渡ったのですが、まだ見ぬ土地へと彼らを向かわせた背景には、当時北朝鮮がさかんに宣伝していた「北朝鮮は地上の楽園である」とのプロパガンダがありました。そのイメージは日本のマスメディアでも好意的に広く流布され、それを信じた彼らは「日本での貧困や差別を逃れられる」、あるいは「祖国に帰る」という希望を抱き、北朝鮮へと移住しました。
希望を胸に海を越えた「帰国者」たちでしたが、実際帰ってみると現地の人からは「異邦人」として見られ、迫害や差別を受けることになりました。日ごとに監視の目は強まり、金正日政権(編注:1994-2011年)の頃からは、「マグチャビ(編注:「一網打尽」を意味する朝鮮語)」という「帰国者狩り」がおこなわれました。たくさんの人が強制収容所に連れて行かれ、多くの人が誰にも知られないうちに亡くなったといわれています。
そうした状況下で生き残り、さらに運よく北朝鮮から逃れて、日本や韓国に渡ることができた人々のことを、このプロジェクトでは元「帰国者」としています。私がお話しできた方の多くは「脱北者」と呼ばれるのが嫌だということで、ネーミングについては参加作家やキュレーターの方たちと協議を重ねた結果、「脱北者って呼ぶのは良くない」と、帰国者を括弧でくくった元「帰国者」という表記にしました。ネーミングに関してのくだりは、コーディネーターとして参加してくださった岡田有美子さんの論考でも触れられています。また、東京藝大でのシンポジウム(2019年6月、GA毛利研究室主催)から、李静和先生の発言の書き起こしを本に収録していますが、そこでも「脱北者」という名指しについての議論が生じました。マイノリティの団体に名前を与えることの、ある種の暴力性について、登壇者で確認し話し合うことで、やはり脱北者という呼称はふさわしくないと判断しました。
― ありがとうございます。今回のプロジェクトで、元「帰国者」の方々に焦点を当てた背景には、在日コリアンとして生まれた琴さんのルーツが関わっていますか。
琴 在日コリアンの方々には、ほとんど全ての人が親戚の中に北朝鮮に「帰国」した人が一人は必ずいると言っても過言ではないと思います。しかし、実際に北朝鮮にいる親戚がどのような生活を送り、どのような思いで暮らしていたかを深く知る人はほとんどいません。私の親戚の中にも北朝鮮に「帰国」した方がおり、親戚の方から送金をお願いされたりという話を子供の頃から聞きながら育ちました。その後、成長し、人文系の大学に進学したのですが、学部の授業での体験に大きく将来への希望を見出すことはできませんでした。そんな中、交換留学に行ったカリフォルニア大学で、映画・映像と現代美術の授業を興味本位で履修したのですが、その際に制作した作品が高く評価されて、美術専攻の学生と並べて大学美術館で展示された経験がありました。その時の指導教員に励まされて、本格的に大学院でアートを学ぼうと決心し、アメリカのCalifornia Institute of the Arts(Calarts)の修士課程に進学しました。卒業制作として制作した映像作品が少しずつ評価され始め、アーティストとしてのキャリアが修士号取得後に本格的にスタートしました。しかし、アートで生計を立てることができる段階ではなかったので、東京芸大の先端芸術表現の博士課程に入学し、その後5年間、博士論文と作品の制作を集中して進めました。博士課程に在籍しながら、1年間韓国のソウル大学で過ごしたこともあります。
― 韓国ではどのような活動をされましたか。
琴 はじめは一人で、もしくは韓国のNGOの方と一緒に国境地帯に2、3回行ったんですね。当初はドキュメンタリーを撮ろうとしたのですが、「撮影する」ことがその脱北した人を危険に晒すことに気づきました。万が一、見つかったら北朝鮮に戻されて強制収容所に入れられるなど、本当に大変な状態になってしまいます。NGOの方も、インタビューや撮影には慎重になっていて、最初は聞き取りだけで撮影は全くできませんでした。私の作品をつくることで危険に晒される人たちがいることに、本当に「申し訳ない」といった気持ちが高まったんです。日本にも、脱北者を預かったりドキュメンタリーを撮ったりという活動で、この業界では有名なジャーナリストがいるのですが、インタビューを受けた方が当局に見つかってしまい北朝鮮で銃殺されたという話を、後に元「帰国者」の方から聞きました。結局、日本にいるから最後まで責任が取れないんです。そういう危険を承知の上で隠し撮りをさせたり、さらには縄張りみたいなものもあって、本当にダークな現実がある。そんなこともあり、このテーマは本当の意味で危険なプロジェクトだなと。それで当時は、ドキュメンタリーではなく、《bloodsea》という詩的な映像作品とインスタレーションをつくって、東京藝大の博士修了作品として発表としました。
藝大の博士課程を終えた2011年からは、韓国で非常勤講師をしながら、ソウル文化財団の助成を受けて韓国に住む脱北した人々とのコラボレーションをやっていきました。脱北した青少年とワークショップをしたり、平壌から来たダンサーを含み構成されている平壌芸術団の方たちとワークショップをしたり、ダンサーを招いてのセミナーを開いて韓国の伝統舞踊のサルプリとか北朝鮮の舞踊チェンガンチュムなど南北の舞踊を紹介しあったりなどの活動をおこないました。プロジェクトは1年半くらいでしたが、その後、交流会とか「チョガッポ」という女性だけの集まりに呼ばれるようになって、ソウルにいる4年間で彼らと交流を深めていきました。
そのうちに、ポツリポツリと脱北した人の中に「帰国者」がいるという話を聞くようになっていきました。梨花女子大学大学院には「北韓学」という北朝鮮を研究する学部があるのですが、そこの博士課程の方と知り合うようになり、調べてみてソウルに住む元「帰国者」と会えることになりました。
― 韓国ではじめて元「帰国者」に会われたわけですね。どんな話が聞けたのですか。
琴 在日コリアンのコミュニティでは、多くの人が「帰国者」は困窮はしているものの幸せに暮らしていると信じられていたのですが、話を伺うと実情はまったく違っていて、想像をはるかに超えた過酷なものでした。強制収容所に入れられたり、脱北する人がいることはご存知の方も多いのですが、それらの方々はあくまでもなんらかの危ない活動に関わっていたり、不幸な境遇に置かれていたりなどの「例外」的な人々だと思われていることが多いと思います。
韓国在住の元「帰国者」へのインタビューは、《Heaven’s Gate》という作品として釜山ビエンナーレ2014で発表しました。それをきっかけにポーラ財団の在外研修でロンドンに1年間研修に行けることになりました。ロンドンでの研修を終えた後、2年ほどの間インドで過ごしました。それは自分にとっての癒しの時間でした。とにかく物価が安く、自然に近いところでゆっくりと過ごしたり、インドの古典音楽を研究したりして心と体をリフレッシュしていくうちに、「あれはなんだったんだろう」と韓国での経験や「帰国者」から聞いた話、日本での無関心について回想するようになるうちに、インドというどこからも離れた場所で、「朝露」の構想が生まれつつありました。
アート系の公募に少しずつ応募していくなかで、ロンドン時代の同期である山本浩貴さんに連絡をとりました。山本さんの博論が在日コリアンのアートについてであり、しばしば情報交換をしていましたし、ご著書の『現代美術史』(中央公論新社、2019年)にもコリアンのセクションがあり、関心領域が近いこともあったからです。山本さんは日本の美術界に知り合いも多く、よくご存じなので「なにか良い公募がありませんか」と尋ねたところ、川村文化芸術振興財団のソーシャリー・エンゲイジド・アート支援助成を勧められました。助成のコンセプトを読み込んで「私にはなにができるだろう」と約1年をかけてアイデアを温めていきました。ソウルにいた元「帰国者」とは既に会っていましたが、日本にも元「帰国者」が住んでいるという話を聞いてたので、そうした方々に会って、一緒にプロジェクトを行いたいと思うようになりました。
思い返せば、私がアメリカから戻りたての2005年頃は、日本では社会的・政治的なアートをつくっている人はほとんどいませんでした。私のような、歴史とか民族とかを口にする人は、全然入れてもらえないような状況でしたが、かれこれ10年以上経っているうちに日本アートにも社会的な作品が増え、また、川村文化芸術振興財団の助成の審査員に、藝大時代の指導教授である毛利嘉孝先生や「在日の恋人」作家であるアーティストの高嶺格さんがいらっしゃったので、もしかしたら採用されるかもしれないと希望を託しました。
― 日本では2011年の東日本大震災を契機に、ソーシャリー・エンゲイジド・アートが盛んになった印象がありますね。
琴 そうですね。私が2005年までいたカリフォルニア芸術大学(CalArts)では、ソーシャリー・エンゲイジド・アートというオブラートに包んだ言い方ではなくて、「アーツ・アンド・ポリティクス」とか「ポリティカル・アート」という言葉が出てきて、新しい潮流として認識されていました。しかしその一方で、アメリカでさえもそうした社会的なアートを排除するメインストリームの動きがあったりと、闘争があることも理解していました。「日本でもやっとこういうのが出てきたんだ」と思ったのを覚えています。
「ソーシャリー・エンゲイジド・アート」という言葉はともかくとして、社会的な批判性を持った作品もOKになっている実情は、私には有利でした。そういうカテゴリーができただけでも、私の居場所を見つけられた気がしたものです。3.11以前は、友人にさえも「社会的な問題を利用して自分のキャリア積んでいるんじゃないの」といったようなこと言われ、私の活動がまったく理解されなかったことを考えると、時代が大きく変わったのだと思います。
― 「朝露」プロジェクトの参加作家はどのように決めたのでしょうか。
琴 社会的なアートが追い風だったとはいえ、日本の風土を考えるとプロジェクトは私ひとりではない方がいい気もしていましたし、元「帰国者」との関わり方もコラボレーションのかたちがいいと考えました。そこで岡田有美子さんにコーディネーターをお願いし、相談しながら決めていきました。私からは山本浩貴さんと竹川宣彰さんに打診しました。理想を言えば、男女バランスを考えて女性にも入ってもらいたかったのですが、当時は日本で社会派のアートをてがける女性の作家さんが少なく、東アジアのポストコロニアルのテーマにも関わるような作品となると、なお難しかったというのがあります。それで山本さんが高川和也さんを連れてきてくれたという感じです。
― 3組4人のアーティストがそれぞれ元「帰国者」やその関係者に会いにいくわけですが、このプロジェクトの難しさはどこにあったと考えていましたか。
琴 韓国で脱北した方たちとワークショップをしたときに一番難しかったのが、信頼してもらうことでした。信頼のない状態から、とりあえず一緒の空間で過ごすというところから始めたんです。どうやって国境を越えてきたのかといった話はあちらもしたくないし、こちらからも聞いてはいけないんだろうという雰囲気がありました。次第に、ぽつり、ぽつりと、「北(朝鮮)にいたときは、子どもだったけど闇市でなにか売りに行った」とか、話し出してくれました。とはいえ、そういう話を長い時間続けることはほとんどありませんでした。
ですから、今回の「朝露」プロジェクトでも、日本に住む元「帰国者」を探してコンタクトするために、とても勇気がいりました。いくつもの団体に行ってようやく連絡先を入手し、いざ電話するときにはドキドキしたんです。でも、実際に会いに行ったら、「よく来てくれたね!」と歓迎されて、初日からいろいろなお話をしてくださいました。「在日の女の子が……いい年ですけども、あちらから見たらね(笑)……会いに来てくれた!」という感じで、嬉しかったようです。やっぱり自分たちのことを、知ってもらいたいんだと。
韓国に住む脱北した方々は「辛かったので話したくない」という傾向がありました。一方で今回は、自分たちの存在や、あちら(北朝鮮)で本当はなにがあったのかを日本人も在日もほとんど知らないので、「事実を知ってもらいたい」と思っているんじゃないかなと。それからこれは私の個人的な話になりますけれど、ジャーナリストなどの人が来てインタビューなどをするわけですが、記事を書くという目的があったのに対し、私はそういう営利・政治的目的ではなく単純に話を聞き、芸術作品をつくりたい、しかも在日というところで、やっぱり嬉しかった面があるんじゃないでしょうか。
― 「朝露」プロジェクトの作品や内容に関しては書籍を読んでもらうとして、2020年の展覧会以降、「朝露」はどのように展開してきているのでしょうか。また、今後、どんな方に伝えていきたいとお考えですか。
琴 2020年11月に北千住BUoYというスペースで展覧会をおこないましたが、その後も、2022年には韓国のDMZ国際ドキュメンタリー映画祭に招待を受け、《朝露》を含めた特集が組まれました。2023年には、ニューヨークのコーネル大学のThe Herbert T F. Johnson Museum of Artで長期間にわたる展覧会「MORNING DEW: THE STIGMA OF BEING “BRAINWASHED”」(23/2/1-6/11)が開かれているほか、2月から3月にかけては、カリフォルニア大学の4つのキャンパスを巡って上映会とトーク・イベント、3月末にはニューヨーク大学でも上映会とトーク・イベントがあるなど、海外での発表が続いています。
「朝露」には前兆のようなプロジェクトがありまして、それが2009年に書籍にもなった『残傷の音』(岩波書店)でした。このプロジェクトの中心となった李静和先生とは、アメリカから帰った直後に出会い、以来私のメンターのような存在として慕っている方です。李先生からこのプロジェクトに誘われて参加し、かけがえのない体験をしました。その後、10年以上経過した後に、私に残った個人的な課題は、当時の著者のほとんどが人文系の方だったことです。岩波書店は人文系ではトップクラスの出版社ですが、次はアート系の出版社から出したかったし、アート界で活躍している方たちにも執筆してもらいたいと考えました。そこで山本さんに相談し、アート分野の本を専門としているアートダイバーを紹介してもらいました。また展示を見てくださったキュレーターの近藤健一さんや崔敬華にも執筆依頼をしました。2000年代には政治的なアートに対して文章を書くとなると、どうしても人文系の方となってしまったのですが、時代も変わり、今回は人文系とアート系とをバランスよくミックスし、アート界や現代美術の観客の方々にも手にとってもらいたいという想いで企画をつくっていきました。
朝露の制作は、断片的な記憶をつなぎあわせる作業でもあり、また、民族への誇りなどの自身の洗脳を解く過程でもありました。こうしたマイノリティの問題を日本のマジョリティの方に見せる時に、「かわいそうな人たちの話」というだけで終わってほしくないという思いは強くあります。ちょうど「朝露」のプロジェクトをおこなっている最中に、あいちトリエンナーレの慰安婦問題が炎上していましたが、私は日本の歴史教育を受けていないので、「何でそこまで怒るのか」がいまだに理解できていません。「朝露」という作品やプロジェクトに関しては、その時につくりたい作品のかたちにしましたが、今後は、今の日本の状況を考えながら、作品のつくりかたをより普遍的にした方がいいのか、あるいはドキュメンタリーとしてきちんとした説明を加えたほうがいいのか悩みます。いまだに編集できていない元「帰国者」へのインタビュー映像を、どのように作品化していくか。それが次の「朝露」となっていくのでしょう。
(2023年2月28日/オンラインにて収録)
琴仙姫(クム・ソニ)
東京都生まれ。アーティスト。2005年カリフォルニア芸術大学 (Cal Arts)修士課程修了。2011年東京藝術大学先端芸術表現領域博士課程修了。2016年ポーラ美術振興財団在外研修員としてロンドンにて研修。apexart(ニューヨーク、2012)、Pump House Gallery(ロンドン、2012)、釜山ビエンナーレ(釜山、2014)、MEINBLAU project space(ベルリン、2017)などで展示。2019年度川村文化芸術振興財団「ソーシャリー・エンゲイジド・アート支援助成」を受け「朝露」プロジェクトを推進。2023年アメリカ・コーネル大学The Herbert T F. Johnson Museum of Artにて「朝露」プロジェクトの特別展開催。
www.sonikum.com
琴仙姫『朝露 ―日本に住む脱北した元「帰国者」と アーティストとの共同プロジェクト』
試し読みはこちら