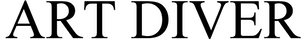石膏デッサン「研究」が必要な理由
いま、「石膏デッサン」は必要なのか?
石膏デッサンの是非については長い間議論が交わされているものの、石膏デッサンこそが美術の基本だという肯定論と、石膏デッサンこそが創造性の敵だという否定論とで、すでに膠着状態である。荒木慎也著『石膏デッサンの100年―石膏像から学ぶ美術教育史』はそうした不毛な「石膏デッサン是非論」の先にある新たなアートの創造のためにも、これまであまり日の当たらなかった「石膏像と石膏デッサン」について深く掘り下げることで、近代の美術教育が遺してくれた蓄積を反芻する試みである。
ここでは、同書冒頭の文章を引用し、荒木が石膏デッサン研究を始めるに至った問題意識について紹介する。
問題の所在
本書のテーマは、筆者と石膏像との個人的な関わりに端を発している。 幼い頃から絵を描くことが好きだった筆者は、高校1年生の時に東京藝術大学への進学を希望し、美術系大学の受験予備校の代々木ゼミナール横浜アトリエに通い始めた。イーゼルや描きかけの絵が雑然と並び、揮発性油特有のツンとくる臭いに満たされた教室に通され、最初に描くように指示されたのは、「トルソ」と呼ばれている石膏像だった。蛍光灯の光に青白く照らされた石膏の質感と、見慣れない古代彫刻の威容に圧倒されながら、それまで美術の専門的な訓練をまったく受けていなかった筆者は、目の前に置かれた奇妙な物体に疑問を挟む余地もなく、ただ無我夢中で描き続けた。まわりの受講生も同じように「トルソ」を描いていたし、何よりも初めて使う木炭と食パンという描画材料と格闘するのに必死で、目の前の「トルソ」が一体なんなのか、まったく疑問に思わなかった。ただ、これまで使ったことのない道具で描く「デッサン」という行為が新鮮で刺激的でもあり、夏期講習は瞬く間に過ぎていった。
美術予備校の経験は非常に興味深かった。高校3年生の時に油絵科を受験することに決定し、本格的に油絵を習い始めたのだが、それでも石膏デッサンは度々描いていたし、また大学によっては石膏デッサンが出題されることもあったため、入試対策としても石膏デッサンは必須だった。筆者のように、美術予備校で訓練を受けた人間にとって、石膏像はごく身近な存在だったし、それが意味するところはよくわからずとも、芸術家を目指すのであれば石膏デッサンは教育の第一歩としてあたり前の行為だった。予備校の廊下には、参考作品として東京藝術大学合格者の石膏デッサンが恭しく展示され、高度な描写力を駆使して描かれたそれらは、当時の筆者にはまるで歴史上の名画のように感じられた。
東京藝術大学油画専攻の入学試験に2度落ちた筆者は、次第に受験のための絵を描くことに興味を失い、芸術学科に志望科を変更し、東京藝術大学芸術学科に入学した。そこで受けた美術史学の授業で、佐藤道信や北澤憲昭が提唱する美術の制度論を知り、その影響を受けて、自らも美術史の制度研究を志すようになった。そして、関心が次第に学術的な研究に移行するとともに、筆者は石膏像のことなど忘れていった。しかし、2007年にヨーロッパを旅行し、各国の美術館を巡る中で、膨大な数の古代彫刻やルネサンスの彫刻に混じって、かつて美術予備校で描いていた懐かしい石膏像のオリジナル彫刻に再会したことが、筆者に再び石膏像への関心を思い出させた。筆者が初めて描いた「トルソ」が「フォーンのトルソ」であり、オリジナルの大理石彫刻がウフィツィ美術館に収蔵されていることを知ったのも、この時だった。
オリジナル彫刻との出会いは、感慨とともに実に奇妙な感覚を筆者の心に植えつけた。美術予備校の教室や倉庫に、まるでガラクタのように無造作に並んでいた石膏像と同じ形のものが、立派な美術館に鎮座していることに違和感を覚えたし、また筆者が受験生だった頃に必死になって描いていた石膏像のルーツを、実は何も知らなかったことにも気づかされた。よく思い返すと、筆者は石膏像について、描き方しか学んでこなかった。画家を諦めて芸術学科に進学しても、受験生時代に必死になって描いたはずの石膏像の歴史的な位置づけについて、何一つ学ぶ機会もなかった。石膏像とはいったい何だったのか。そもそも、なぜ美術予備校ではあたり前のように石膏デッサンから勉強を始めたのだろうか。ヨーロッパに無数にある彫刻のうち、なぜ「フォーンのトルソ」が石膏像になって日本に入ってきたのか。この時、受験生時代に受けた教育体験、とりわけ石膏像の存在と、美術制度研究の二者が融合し、筆者は、自身の原点を再び見つめ直すように、日本の石膏像の研究を開始した。
本書を個人的なエピソードから始めたのは、筆者の体験が、日本で美術教育を受けた者の多くに共通する体験であり、同時に、日本の美術教育の歴史に幾重にも織り込まれた文化の受容と改変の過程を象徴する出来事だからだ。 1896年に東京美術学校西洋画科が設立されて以降、石膏デッサンは美術教育の基礎として日本に定着し、およそ100年間続けられてきた。日本の美術教育の歴史は、石膏像とともにあった100年と言っても過言ではない。この歴史を解き明かせば、筆者がヨーロッパ旅行で感じた違和感の原因を理解できるのではないか。研究を始めた当初、石膏像は非常に魅力的な対象に見えた。
しかし、石膏像の研究は当初は難航を極めた。そのもっとも大きな理由は、石膏像に関する既存の文献や資料が、肯定にせよ否定にせよ、感情的な論調が目立つものばかりで、客観的な判断をしばしば困難にしたためである。それもそのはずで、芸術家や美術評論家たちの間では、石膏デッサンはすこぶる評判が悪かった。石膏デッサンは個性を殺して対象を正確に再現描写するための技術訓練で、オリジナリティを重視する現代的な価値観にはそぐわないといった意見や、石膏デッサンはもはや単なる入試対策でしかなく、芸術家になるためには何の役にも立たないといった意見は、筆者も受験生時代から度々耳にしてきたし、今日でも石膏デッサンを批判する際の常套句となっている。石膏デッサンは最近まで美術予備校の定番の課題だったため、美術系大学進学希望者は、形を詳細に記憶するまで繰り返しデッサンすることを強いられていた。要するに、日本で美術の道を志すならば、ごく近年までは何らかの形で石膏デッサンを通過せざるを得なかったのが実情であり、石膏デッサンが批判されるのも、芸術家たちが石膏像に対して受験の苦い記憶を重ね合わせていることに起因するのだ。
石膏像の研究を困難にした、もう一つの要因は、先行研究の少なさだった。美術アカデミーの本場だったヨーロッパでは、石膏像の歴史に特化した研究をいくつか見つけることができるものの、日本の美術教育学や美術史学で石膏像や石膏デッサンを中心に扱ったものは稀である。このため、日本でよく見られる石膏像のオリジナル彫刻の名称を特定するといった単純な作業でも、ヨーロッパ各国の美術館の所蔵品や、石膏像製作工房の目録をしらみつぶしに精査するところから出発しなければならなかった。
石膏像や石膏デッサンに対する否定的な見方が大勢を占める中、美術史の一分野としての石膏像の研究は、現在でも極めて限られている。芸術家の体験談やインタビュー記事、石膏デッサンの技法書こそ多数存在するが、そこで繰り返されてきた内容は、石膏デッサンに本質的・根源的な価値を見出し、「デッサンこそが美術の基本である」と主張する素朴なデッサン本質主義か、あるいは入学試験に頻出する石膏像のデッサンのポイントを解説した、受験対策としての技法論のいずれかだった。同様に、石膏デッサン教育を批判する言説も、20世紀初頭から、「デッサン教育が若者の創造性の芽を摘む」という感情的な批判が今日に至るまで繰り返されてきた。石膏デッサンこそが美術の基本だという肯定論と、石膏デッサンこそが創造性の敵だという否定論の間で、美術教育家たちの意見は二分し、幾度も対立しながら、明確な結論を産み出さずに今日に至る。感情的な対立が繰り返されてきた歴史的経緯も、本書で明らかにするが、その根本にあるのは、石膏デッサン教育の歴史的な成立に対する検証の不足で、それゆえに学術的な議論の蓄積がされず、漠然とした石膏デッサンに対する批判が繰り返されてきたと言える。
一方で、青春の1ページとして石膏像に対して著しい愛着を感じる者が多くいるのも事実である。石膏像は苦しい受験勉強の象徴であると同時に、しばしばフェティッシュの対象ともなった。その一例として、玩具企画・製造会社のユージン(2009年にタカラトミーアーツに改称)が 2005年に販売したカプセルトイ「石膏デッサン入門」がある。これは美術系大学入試に頻出する石膏像10体のフィギュアで、街の自販機で購入できるいわゆるガチャガチャである。通常の採算ラインが10 万個のところ30万個近く売れるヒット商品となり、2009年には続編の「石膏デッサン入門2」が販売された。本商品を企画した、東京のアンティークショップ「EXPO」代表の鴻池綱孝によると、これは東京藝術大学彫刻科の学生が原型製作を手がけた商品だった。東京藝術大学で原型師を募集した結果、想像以上の立候補者があり、石膏像が美大生にとっていかに特別な存在であるかが感じられた、と言う[註1]。
より新しい例として、2015年2月にザリガニワークスがKADOKAWAおよびホルベイン画材と提携して発表した、「石膏ボーイズ」という架空のアイドルユニットが挙げられる。YouTubeのKADOKAWA オフィスチャンネルに投稿されたプロモーション・ビデオの説明文には、次のように書かれている。
美術の授業、デッサンなどでお馴染みの数ある石膏像の中から4 体(マルス・メディチ・聖ジョルジョ・ヘルメス)をピックアップしユニット化させたもの。石膏像をこれまでにない角度から見つめなおし、「美しい人」「イケメン」として扱い、あたかも芸能人であるかのような見せ方で活動するプロジェクトです![註2]
「石膏ボーイズ」は、2016年にアニメ化もされ、個性豊かな性格を与えられた4体の石膏像と、「彼ら」のマネージャー役を任された石本美希というキャラクターを中心に繰り広げられるコメディとなった。西洋美術史の規範であるはずの石膏像がアイドルグループとなる滑稽さと、マネージャーが美術系大学でやらされた石膏デッサンのトラウマを抱えているという設定は、日本における石膏デッサン教育の問題をアイロニカルな笑いに転換し、ポップ・カルチャーとして消費することが可能なほどに、石膏像が社会に受け入れられていることを示している。
あるいは、より美術史的な文脈から、石膏像や石膏デッサンを芸術作品の一部として取り込む芸術家も存在する。例として、現代美術家の会田誠は、巨大な「ブルータス胸像」の石膏デッサンの上部に、皮肉を込めて現代美術専門誌『美術手帖』の略称であるBTという文字を描いた《BT》という作品を発表した。また、会田が2005年にサンフランシスコで開催した展覧会に参加した芸術家グループのChim↑Pomは、2005年に映像作品《Chim↑Pom:P. T.A.》を発表し、その中で受験に失敗したメンバーが「ブルータス胸像」を破壊する《BRUTUS》というパフォーマンスを行った[註3]。これらの例を見ても、石膏像は単なる教材の一つではない、極めて特殊な感情に彩られた存在だということがわかる。
いずれにせよ、もともとは古代彫刻やルネサンス彫刻の複製で、西洋美術のカノンを学ぶための教材だった石膏像は、憎しみであれ愛着であれ、本来の文脈とは大きく異なった文脈で受容されてきた。これらの例が示す、西洋美術の美的規範の脱神聖化、受験教育との深い関係、そしてそれに伴うノスタルジーの付与やマスコット化は、一体どのような歴史的・社会的要因に起因するのだろうか。また、芸術家にとって身近な存在でありながら、同時に素直に受け入れることが困難な存在でもあった石膏像を、どのようにして研究対象として扱えば良いのであろうか。結果的に、筆者は、石膏像に対する感情的な言説を排除するのではなく、感情のもつれを時系列的に整理し、言説の歴史的変遷を描きだすことで、最終的に石膏像が「悪者」とされるに至った文脈や過程を見極めることに努めた。そして、石膏像の元になったオリジナル彫刻や、石膏像が教材として日本に到来した過程を調査し、美術教育における石膏像の位置づけの変遷を把握することに努めた。日本の美術教育にとって石膏像とは何だったのか、という問いは、基礎情報と地道な分析を積み重ねることで初めて考察が可能になる。このような目論見の下に、筆者は石膏像と石膏デッサンの研究を始めることにした。
[1]鴻池綱孝(EXPO 代表)へのインタビュー、2008年11月11日。
[2]石膏像が芸能活動!?『石膏ボーイズ』PV -YouTube(www.youtube.com/watch?v=gDv3HPkvYTs)2015年2月14日閲覧。
[3]《Chim↑Pom:P.T.A.》のDVDは廃盤になっているが、《BRUTUS》の映像はYouTubeで閲覧可能である。BRUTUS / Chim↑Pom – YouTube(http://www.youtube.com/watch?v=b4Yi3jNsrCs)2012 年11月1日閲覧。
(荒木慎也『石膏デッサンの100年―石膏像から学ぶ美術教育史』アートダイバー、2018年、pp.12-17より抜粋、編集)
荒木慎也『石膏デッサンの100年―石膏像から学ぶ美術教育史』